公開日: 2026年01月27日 / 更新日: 2026年01月27日
コラム
生成AIと歴史と文脈と物語

「歴史マニア」と呼べるほどマニアではないけれど、歴史は好きだ。細部のエピソードが積み重なり、やがて一つの大きな流れや物語として立ち上がってくる、その過程に強く惹かれる。
長い歴史ものの本を読む作業ってベートーヴェンの音楽とかミニマルミージックの気持ち良さにすごく似ているところがある。
ベートーヴェンってシンプルな音形が色々な組み合わせでちょっとずつ積み重なっていく。テーマとなっている音形は本当にシンプルなもので、例えば有名な運命の「ジャ・ジャ・ジャ・ジャーン」の4つの音でできているけど、それの積み重ねの先に体の全身が痺れるほどの高揚がある。
ショート動画文化で数十秒にトリミングされた音楽に慣れてしまったけど、時々こうやって文脈の長い音楽を聞いてみると、「塵も積もれば山となる」という言葉を深いレベルで体感できる気がする。
歴史とは文脈を語ることである
音楽の場合はそこに作った人の強い意志の力があるけれど、歴史の魅力は偶然の重なりに過ぎないかもしれない一連の出来事が、語り手の手にかかってみると、何かの意思が介在していたのではないかと思えるほどの力強いストーリーラインが立ち上がってくるように感じられることだ。
もちろん、その物語性は自然に浮かび上がるものではない。
無数に存在する出来事や証言の中から、何を中心に据え、何を周縁に追いやるのかを選び取るのは、常に歴史家の仕事である。どの視点を採用するかによって、同じ時代であってもまったく異なる歴史像が描かれる。
だからこそ、歴史を語るという行為は、事実を並べることではなく、文脈を語ることに他ならないのではないか、と思えてくる。
個々の出来事が、どのような条件のもとで生まれ、どのような関係性の中に置かれていたのか。
その配置と意味づけにこそ歴史の醍醐味がある。
最近、ずっと生成AIが人間の思考にもたらす甚大な影響について考えることが多くなった筆者であるが、ここ一年で読んだ生成AI関連の記事のなかで一番印象に残っているのはNew York Timesに取り上げられた「A.I. Is Poised to Rewrite History. Literally.」(AIは歴史を書き換えようとしている。文字通りに)と題する記事だ。
「見つけられるが、理解できない」時代
この記事は、生成AIが歴史研究やノンフィクション執筆の現場にどのような変化をもたらしつつあるのかを、複数の歴史家の具体例を通して描いている。
記事に登場するのは、A史料を読ませ、要約させ、異なる資料間の欠落を指摘させるとどまらない生成AIの可能性が批評的に論じられている。
しかしこの記事の射程は、単なる「AIは便利か、危険か」という技術論にとどまらない。むしろ印象的なのは、コンピュータとインターネットの登場が、すでに知のあり方を大きく変えていたという指摘である。
記事は、2016年にララ・パットナムという歴史家が提示した議論を引きながら、コンピュータとインターネットの普及が、過去に関する情報量を指数関数的に増やすと同時に、それを検索し、ふるいにかける力を人間に与えてきたことを指摘する。
その結果、私たちは、ほとんどすべてが手に入るかのような感覚の中に置かれるようになった。しかも、膨大な検索結果が次々と提示されることで、「自分は全体像を把握している」と思い込みやすくなっている、と指摘している。
つまり「わかったふり」をしやすくなってきたということだ。
「歴史家は初めて、どこを探せばよいかを知らなくても、史料を見つけられるようになった。しかし、見つけた史料を正確に読み、その重要性を評価する能力が、同じ速度で加速するわけではない。」
「発見」は加速したが、「理解」がそれに伴うわけではない。
この指摘がなされたのは生成AIが普及する前の2016年のことである。
インターネットの普及に伴う情報へのアクセスに対して、こういった危惧があったのであれば、生成AIによって情報収集が驚愕的に簡単になってしまった現在であればなおのことだろう。
実際に、個人的な体験を振り返ってみても、文脈は無視せざるを得ないことが多くなった。
というよりも、これだけの情報量のなかで、それぞれの文脈を考慮して冷静に物事を判断するだけの時間的リソースも認知的リソースもほとんど余っていないというのが正直なところの現状だ。
文脈を正確に理解することは、情報を沢山集めるということとは本質的に違う種類の作業だ。
むしろ、正しく文脈を把握し、説得力のあるひとつの物語を立ち上げるためには、見立てる力が何よりも大事になってくる。
あるいは、それは細部への異常な執着から姿を現す場合もある。
物語の核
この記事の軸となっているのは、Google Labsの編集ディレクターでもあり、ポピュラーヒストリーの筆者でもあるスティーブン・ジョンソンの逸話である。NotebookLMという生成AIを次回の作品の執筆に活かそうとしている試みが現在進行中のものとして語られており、とても興味深い。
私が特に面白いと感じたのが、彼がGoogleの製品を宣伝する立場として、歴史における生成AIの可能性をかなり前向きに捉えている一方で、「事実をどのように提示するか」というストーリーテリングの骨組みを作る作業を決して生成AIには委ねていない点だ。
19世紀半ばのカリフォルニア・ゴールドラッシュを、ヨセミテ渓谷と先住民の視点から描き直すというのが彼の次作のテーマであるが、彼は生成AIに作業させる前に、うまくいくであろう物語の構造をすでに持っている。
チャールズ&レイ・イームズの『Powers of Ten』に着想を得て、時間スケールを指数関数的に縮めながら物語を進めていくというものだ。
百万年単位の地質学的時間から始まり、人類の定住、社会の形成、植民と緊張の高まりへと視点を次第に絞り込み、最終的には1851年のヨセミテ侵攻という一点に収束させる。
彼が集めた膨大な量の史料をその構成をもとに再構築する作業を生成AIに任せてみたということなのだ。
つまり最初の見立て、あるいは仮説を立てるという肝心の部分は生成AIに任せていない。
もちろん、この構成がうまくいきそうだ、と彼に思わせたものがなんだったのかは明言されていない。
それは経験からくる勘だったかもしれないし、ちょっと変わったことをしてみたい、という冒険心だったのかもしれない。
そもそもその構成がうまくいったとも書かれていない。
いずれにしても、歴史を語る際の構成は全体のナラティブを左右する。
その枠組みが、歴史に「解釈」を明確に与えるものではないにしても、読者の視点に大きなインパクトを持つものであることには変わりない。
回り道を選び続ける感覚
この記事を読んでいて、もう一つ強く印象に残ったのが、ロバート・キャロの話だった。
リンドン・ジョンソンの伝記に50年を費やし、89歳になった今もなお、その最終巻が完成するのかどうかが注目されている人物だ。彼が集めた資料は、すでに一部がニューヨーク歴史協会に寄贈されているが、その量は約45.7メートルにも及ぶという。
数字だけを聞くと、もはや執念とか狂気といった言葉の方がしっくりくる。
記事は一瞬、こう問いかける。もし生成AIが、この膨大な資料の一部でも要約し、整理してくれていたなら、キャロはこの50年でもっと多くの伝記を書けていたのではないか、と。確かにそうかもしれない。効率という観点から見れば、それはもっともな想像だ。
けれど、すぐに続く一文で、私はハッとさせられた。
すべての資料に自分の手で触れずにはいられないという執着、果てしない読書の厳密さを、そのまま文章に注ぎ込もうとする姿勢がなければ、たとえAIに助けられていたとしても、それはロバート・キャロではなかっただろう、というのだ。
この一文を読んだとき、私は激しく同意した。
違いをもたらすのは、しばしば合理性からは説明しきれない人間の偏りや執着なのだ。
細部にこだわりすぎること。時間をかけすぎること。何度も同じ資料を読み返してしまうこと。
そうした行為は、効率や生産性という尺度で見れば、無駄に映るかもしれない。けれど、キャロの仕事を思うとき、それらは単なる非効率ではなく、歴史に固有の重さやニュアンスを与えるために、どうしても必要な回り道のようにも感じられる。
生成AIがどれだけ進化しても、この「回り道を選び続ける感覚」そのものまでは、代替できないのではないだろうか。
「夢遊病者たち」にみる細部の力と曖昧さの力
この記事を読みながら、私は数年前に読んだクリストファー・クラークの『夢遊病者たち』のことを思い出していた。第一次世界大戦の開戦過程を描いたこの本は、細部の集積が持つ力を体現したような本だった。
第一次世界を巡ってはドイツをはじめとするヨーロッパの列強同士の政治的力学を軸に書かれることが多いようだが、この本ではそうした大きな構図をあえてぼやかそうとしているところがある。
バルカン半島でのゲリラ運動の詳細に焦点を当てた箇所が多く、それがいかにサラエボ事件へとつらなっていったか、ということが一つの軸になっている。
この本は、読者に安易な理解を許さない。誰か一人の悪意や決定的な瞬間に責任を押し付けることを拒み、各国の指導者たちが、それぞれ限られた情報と制約の中で、少しずつ事態を悪化させていく様子を、執拗なまでの細部で描き出す。
複線的にいろいろな要素が絡み合って行く様子が本当にうまく描かれている。
もし一つでもボタンを掛け違っていたら歴史はまったく違う方向にいっていたのではないか、という印象を持った。
「夢遊病者たち」は、読者を「わかったつもり」にさせないのだ。その遅さ、不確実さ、逡巡の積み重ねこそが、この本の一番の魅力だったように感じた。
語り方を選ぶということが、物語の重要な構成要素のひとつなのだと感じさせられた作品でもあった。
「遅さを組み込む知性」
つまり、語り手である人間がどれだけの意思と意図を持ち得るか、ということだ。
生成AIによて情報へのアクセスはますます用意になった今、文脈を深く理解する力が問われている。
この原稿を作成するためにChatGPTと沢山の壁打ちを重ねた。
特に長文の新聞記事の要約をさせたりとライティングでもかなりの助けを借りた。
その過程でChatGPTが出してきた言葉に印象深いものがある。
「遅さを組み込む知性」という言葉だ。
私がこの一年、生成AIとがっぷり四つになって向き合った中で私が考えてきたテーマを端的に表した言葉だ。この言葉がChatGPTから出てきたというのがなんとも皮肉である。
曖昧さを抱えたまま、一つにことにじっくり悩み抜ける知的体力が持てるかどうかが、AI時代を生き抜くためには求められている気がしてならない。
OpenAIのコンテンツ・デザイナーの求人には求められている素質として
Enjoy tackling ambiguous problems and shaping them into a clear vision
つまり
曖昧な課題に主体的に向き合い、それを明確なビジョンへ落とし込むことを楽しめること
が挙げられている。
正解のない問題に対してどれだけ意欲的かつクリエイティブに取り組めるか、というふうに捉えることもできるのかもしれない。
歴史を書くというのはまさに「正解のない問題に対して歴史家なりの視点を提供すること」だとすれば、歴史を学ぶということは、そうした独自の視点を探り出す方法をも学ぶということ、といえるかもしれない。
生成AIがどれほど進化しても、出来事をどう配置し、どの細部に意味を見いだし、どんな物語として語るのかを見立てる作業は、人間の側に残り続けて欲しいと思う。
その意味で、歴史を学ぶということは、過去の知識を蓄えることではなく、「遅さ」を引き受けながら文脈を組み立てる知的態度そのものを身につけることなのだと思う。
それは時には大胆に仮説を立てて、細部をそれに追従させようとする能動的な態度に現れるのかもしれない。あるいは、細部に執念的にこだわりぬくことで全体像が揺さぶられることだってある。
「その往復運動を引き受けられるかどうかが、AI時代の知性を分けるのではないか」とChatGPTは言っている。
人間の持つこの偏りと執着が、歴史に繊細なニュアンスを添えていくのと同じように、業務上の判断にも深みを与えてくれるものとなるのだと強く感じている。
書いた人:酒井 志郎
ITエンジニア。C++, VB, C#などを使ったプログラミングをシステム開発会社で10年間以上経験した後、
ロケットスタートに転職。kintoneのカスタマイズはじめロケスタのIT部分に幅広く携わる。
-

「人を育てる姿勢」を、まっすぐに伝えるために【株式会社ライフステップ様 Webサイトリニューアル事例】
株式会社ライフステップ様
-

少しずつ整えて、育てていくDX
株式会社人財企画様
-

施設の“らしさ”を、もっとわかりやすく、もっと身近に【社会福祉法人 静香会様Webサイトリニューアル事例】
社会福祉法人静香会様
-
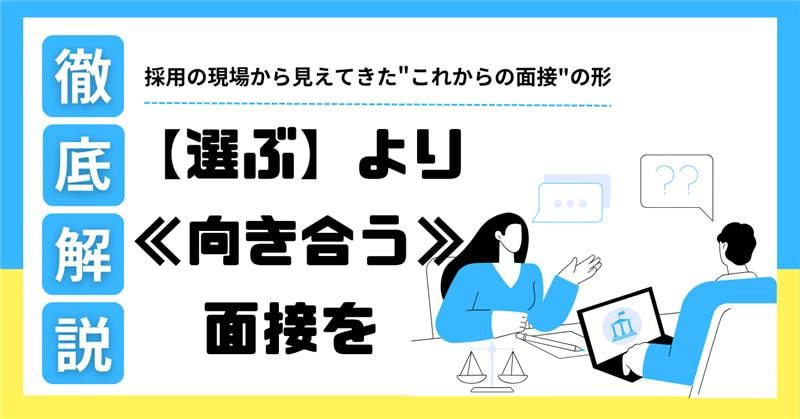
「選ぶ」より「向き合う」面接を──最近の採用事情と“これからの面接”のヒント
-
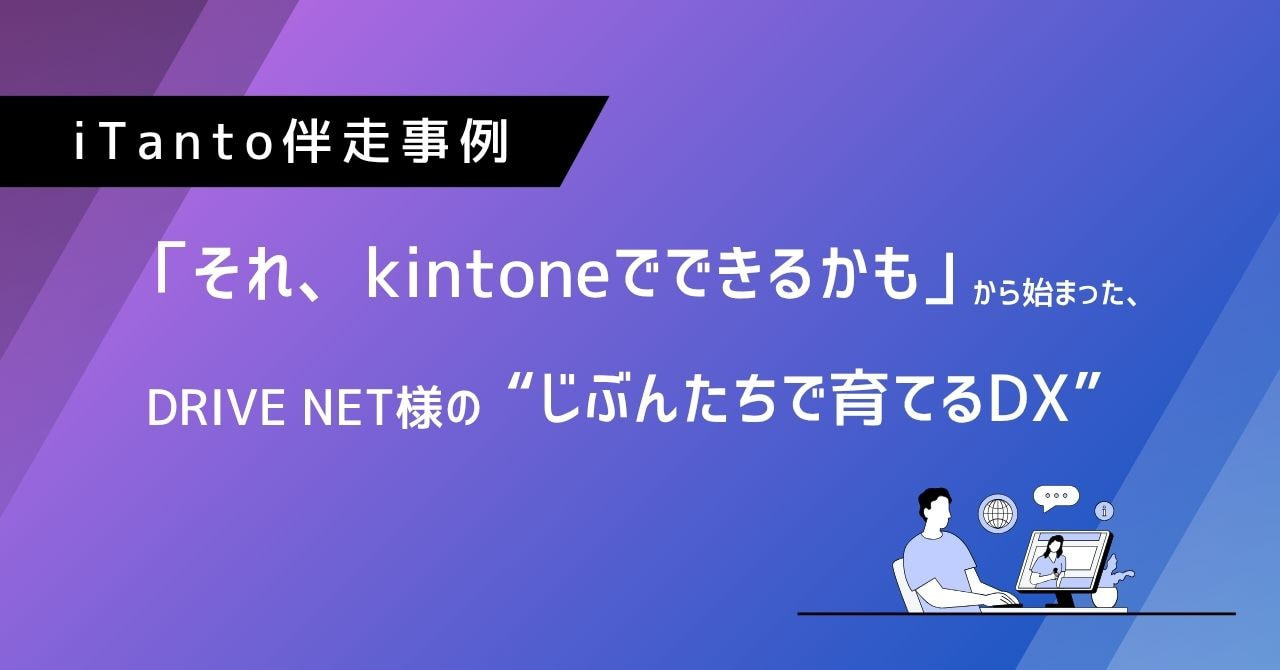
「それ、kintoneでできるかも」から始まった、DRIVE NET様の“じぶんたちで育てるDX”
DRIVE NET株式会社様
-

「伝わる」ことで広がる価値【株式会社サンメディカルサービス様Webサイトリニューアル事例】
株式会社サンメディカルサービス様




